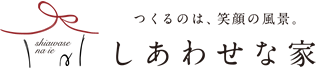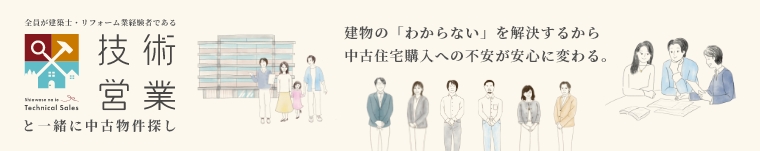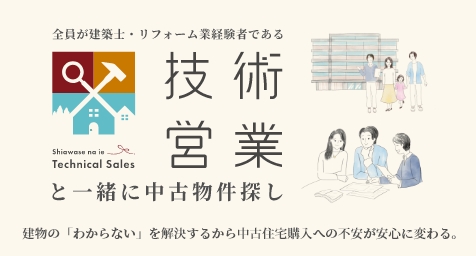2025.07.10
プロが解説する中古住宅の値引き交渉について

「この物件、もう少し安くなりませんか?」
不動産仲介の現場で、必ずといっていいほど出てくる質問です。
中古住宅の購入を検討している人にとって、“いくらまで下げられるか”はとても現実的な関心ごと。けれど、やり方を間違えると、せっかくのチャンスをみすみす逃してしまうこともあるのです。
不動産のプロとして、そして実際に仲介の現場で何百件とやり取りしてきた立場として、“値引きのリアル”をお伝えします。
目次
| 1. | 値引きの「相場」と「上限」はどこか? |
| 2. | 値引きに応じやすい物件の特徴 |
| 3. | 値引きが難しい物件の特徴 |
| 4. | 代表的な失敗例 |
| 5. | 値引きよりも効く“実質コスト削減”の考え方 |
1.値引きの「相場」と「上限」はどこか?
一般論としての目安は端数くらい、ただし条件次第
多くの仲介実務で体感するのは、中古住宅の価格には80万円がついているケースが多いですが、この「端数の値引きが現実的な範囲」です。3980万円の物件なら、80万円の減額が交渉成立する可能性のあるラインと考えられます。
ただしこれは“一般論”にすぎません。以下のような条件が揃っていると、それ以上の値引きが成立するケースも多々あります。
- 価格が周辺相場より明らかに高く設定されている
- 長期間売れ残っている(半年以上)
- 売主が空き家の管理負担や税負担から早期売却を希望している
実際に筆者が担当した案件でも、2980万円で出ていた物件が2500万円で成立したケースがあります。これは売主が遠方に転居済みで、空き家の管理が困難だったこと、近隣に競合物件が複数存在していたことが影響しています。
また、マンションか戸建かによっても大きく値引き余地が変わってきます。マンションは類似物件が多く価格が比較的明確であり、売主も相場を把握していますよね。なので、驚くような値引き率になったというケースはあまりないです。
それに対して戸建は、土地や建物の個別性が高く、価格設定が売主次第な部分も多いので、「リノベーション前提での購入」を考えている場合、設備の劣化や間取りの古さを価格に反映してもらう形で、値引きの余地が大きくなりやすいのが戸建てです。
2.値引きに応じやすい物件の特徴
値引きに応じやすい物件の特徴は、下記のようなものが挙げられます。
売却理由が“資産を処分したい”というニーズ
売却理由が「相続」「転勤」「住み替え」など、ライフイベントに付随して、“資産を処分したい”というケースでは、売主が「売ること自体を目的」としているため、価格に対する執着が比較的少ない傾向があります。
とくに相続物件は、実際に売主が住んでいないことも多く、感情的なこだわりが薄れがちです。「思い入れがあるから高く売りたい」という意識よりも、「現金化して分配したい」「維持コストを早く手放したい」といった実務的な目的が強くなるため、交渉の余地が生まれやすくなります。
また、転勤や住み替えによる売却も「次の生活のステップに進むための手続き」と捉えられていることが多く、ある程度の価格譲歩も想定のうちというケースが見られます。売却理由が明確で現実的であればあるほど、「価格で揉めたくない」という心理が働き、柔軟な判断につながりやすいのではないかと考えています。
市場での掲載期間が長い
売却活動が半年以上続いている、あるいは1年を超えるような長期掲載の物件には、売主側に「そろそろ決めたい」「このままでは売れないかもしれない」という焦りが生じやすくなります。こうした心理的背景があると、価格面の譲歩にも応じやすくなります。
特に、ポータルサイト(SUUMO・アットホームなど)で確認できる“初回掲載日”は、実際の売却活動のスタート時期とは異なることが多く、正しい情報とは限りません。スタート時期を正確に知ることは難しいケースもありますが、不動産会社に確認すると概ねわかりますので、頼りにするといいでしょう。もし初回掲載日から半年以上経過しているようであれば、「条件を見直してもらえませんか」と交渉する材料になります。
また、長期掲載=市場からの反応が薄い、という事実も買主側にとって有利です。競合が少ないタイミングを狙って、冷静に価格交渉を進めることができます。
リフォーム・修繕の必要が大きい
建物に経年劣化が見られる物件、特に給排水管の老朽化や屋根・外壁の補修が必要なケースでは、購入後に多額の工事費用がかかることが予想されます。そのため、あらかじめその分を価格に反映してもらう形での交渉が現実的になります。
具体的には、専門家のホームインスペクションやリフォーム会社からの見積書を添えて、「購入後に●●万円の改修が必要となる見込みがあるので、その分も考慮いただけませんか」といったアプローチもアリです。
とくに築年数が30年以上の物件は、新耐震基準との整合性やインフラ設備の更新タイミングなども含めて、追加費用がかさむリスクが高まります。そうした“実費ベースの根拠”は、売主にとっても納得しやすい交渉材料となります。
価格の変遷が頻繁にある
価格がすでに2〜3回改定されている物件は、売主が市場の反応を見ながら「希望価格では売れない」という現実に直面してきたことを示しています。つまり、売主のプライオリティが、売ってしまいたい>価格を下げるという状態です。
ポータルサイトでは「価格履歴」や「掲載価格の推移」を確認できることが多く、そこから売主の交渉姿勢を推察できます。たとえば、当初4,000万円以上で出ていた物件が、半年で3,480万円に下がっていれば、「価格調整は視野に入れている」と見てよいでしょう。
買主側としては、「既に価格を下げている=さらに応じてもらえる余地がある」という一歩踏み込んだ交渉が可能になります。ただし、“値下げに応じてきた理由”が「反響が薄いから」なのか、「内部的に売却を急いでいるから」なのかによっても判断が分かれます。売主の事情や掲載時期も合わせて総合的に読み取ることが大切です。
3.値引きが難しい物件の特徴
売主が居住中かつ売却に“未練”がある
売主が現在居住している物件は、感情的な執着が強く影響しやすいため、価格交渉に応じる可能性が低くなります。特に、売却理由がはっきりしていない場合、売主は「この家を手放したくない」という気持ちが強く働いている可能性があります。このような場合、値下げ交渉が難航することが予想されます。
また、売却理由が不明確なまま掲載されている物件は、相場をきちんと把握していないこともあります。「とりあえず出してみた」状態では、売主側が価格に対して強気になりやすく、交渉で有利に立つことが難しくなります。売主にとっては「手放したくない」「何となく売ってみた」といった心理が働いており、交渉における譲歩を引き出すのが難しい場合が多いです。
販売開始から1ヶ月以内
新しく市場に出てきたばかりの物件は、売主がまだ希望の価格で売れることに自信を持っているため、交渉で価格を下げてもらうのは非常に難しいことが多いです。このタイミングでは、売主は「買い手が現れるまで待とう」と思っていることが多く、値下げに対しては消極的になります。
売主は、物件が新規掲載されてからまだ期間が短いため、いわゆる「様子見」の段階にあります。このタイミングで強気に価格交渉をしても、売主側は「もう少し待てば価格を受け入れてくれる買主が現れる」と考えているため、交渉は難航するでしょう。
そのため、このような物件に対しては、時間が経過して市場に反応が見られるようになるまでは、値引き交渉を避ける方が無難です。
築浅かつリフォーム済の物件
築年数が少なく、リフォームが完了している物件は、特に人気が高い傾向にあります。こうした物件は買主のニーズにマッチしやすく、即入居可能な状態が整っているため、市場での競争が激しくなりやすいです。そのため、売主にとって価格を下げる理由が少なく、価格交渉に応じる姿勢はあまり見られません。
また、リフォーム済の物件は「すぐに住むことができる」「手間をかけずに入居できる」といった付加価値があり、一般的にはその分人気が集中します。人気物件であれば、買主側の交渉余地が限られるため、売主が強気の価格を維持しやすい状況です。
このタイプの物件に関しては、価格が少しでも下がる可能性を期待するのは難しく、交渉を進める際には冷静に市場価値を理解し、条件を整えることが重要です。
4.代表的な失敗例
「値引き希望の理由は?」に答えられない
もっともよく見られる失敗は、感覚的な値引き要望だけを伝えてしまうことです。
たとえば「100万円くらい安くなりませんか?」といった要望は、売主から見れば「とにかく安く買いたいだけ」という印象を与え、好意的に受け取られにくくなります。
価格交渉は“値切り”ではなく、“合理的な再調整”の提案です。そのためには、客観的な根拠が必要です。以下のようなデータを揃えて、論拠を構築しましょう
周辺の成約事例(直近3〜6ヶ月)
→ SUUMO・ホームズなどのポータルサイトで、実際にいくらで売れているかを確認
同じエリアの坪単価比較
→「本物件は坪90万円ですが、近隣の同等条件では85万円前後が主流です」など、相場との乖離を指摘
リフォーム費用の概算
→ 実際の見積書があればベスト。なければ過去の相場などをもとに提示(例:「水回り+内装で200万程度の費用が見込まれます」)
こうした“数値ベースの論理”があると、売主としても「それなら多少の調整もやむを得ないか」と判断しやすくなります。
「リフォームにお金がかかるので」は言い方次第
老朽化した物件などでは、購入後にリフォームが必要なケースも多く、それを理由に価格交渉をするのは自然です。
しかし、伝え方を誤ると、売主に「それはそちらの事情ですよね?」と反発されてしまいます。
NG例:
「直すのにお金がかかるんで、安くしてもらえませんか?」OK例:
「築30年で水回りの設備も旧式なため、交換に少なくとも200万円ほどの費用がかかる見込みです。もちろんこれは私たちの事情かもしれませんが、購入後すぐに費用負担が発生する点をご理解いただき、150万円ほど価格の調整をご相談させていただければと思いまして…」
このように、“相手の立場を尊重した言い回し”を意識するだけで、同じ主張でも受け取られ方が大きく変わります。
「売主には関係ない話かもしれませんが…」と前置きすることで、謙虚な姿勢と誠意が伝わり、印象が良くなります。
買主の態度が“敵”になると成立しない
価格交渉は、単なる取引ではなく人と人との信頼関係の上に成り立つプロセスです。とくに売主が現在も住んでいる物件では、購入希望者の態度や言葉に強く反応することがあります。
避けたい言動例:
「この壁紙、正直かなり汚いですよね」
「間取り、ちょっと微妙じゃないですか?」
「どうしてこんな場所にキッチン作ったんですか?」
このような発言は、たとえ事実であっても、売主の感情を逆撫でし、「この人には売りたくない」と感じさせる原因になります。
売主にとって、その家は「生活の記憶が詰まった大切な空間」であることを忘れてはいけません。
信頼関係が築ければ、売主も「この人なら気持ちよく取引できそうだ」と思い、柔軟な判断をしてくれる可能性が高くなります。
5.値引きよりも効く“実質コスト削減”の考え方
ここまで「価格交渉」にフォーカスしてきましたが、実務上は「値引きよりも効くコスト削減策」もあります。
売主の都合に寄り添う“条件交渉”
実際の価格以外に、売主の希望に配慮することで、“実質的なメリット”を得られるケースも多くあります。
たとえば、
- 売主の希望する引き渡し日を優先
- 引越し猶予を認める
- 残置物の処理を柔軟に受け入れる
など、売主の心理的ハードルを下げる条件を提示することで、結果として価格面でも譲歩を引き出せる可能性があります。
筆者が経験した例では、売主が「引越し準備に3ヶ月必要」と申し出たのに対し、「その分50万円値引きする」という提案が通ったケースも。
値引きとは、“金額の交渉”であると同時に“関係性の交渉”でもあります。
値引きは、“言えば下がる”というものではありません。
市場価格・売主事情・物件状態という三要素をどう読み取り、それに応じてどのタイミングで、どんな姿勢で臨むか。
交渉は情報戦であり、相手との信頼関係を築く“コミュニケーション設計”でもあります。
「うまく買いたい」と思ったとき、単に価格だけでなく、「どうすればお互いに納得感ある着地ができるか」を一緒に考えること。
とはいっても、住宅を購入するなんてそう何度もあるイベントではなく、「わからない」だらけだと思います。
しあわせな家では、建築士・リフォーム業経験者である「技術営業」が中古住宅探しからサポートさせていただき、素敵にリノベーションされたお客様の施工事例を多数ご紹介しておりますので、ぜひご覧ください!