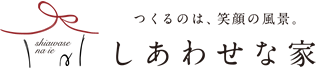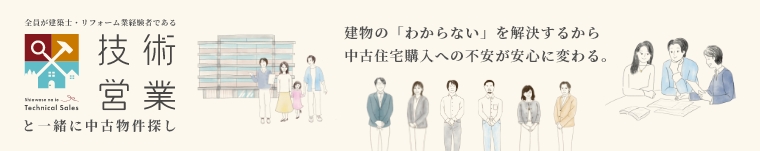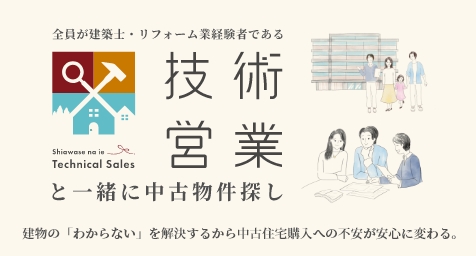2025.07.04
中古戸建を買ってリノベすることのデメリットが気になったら読んでほしい記事

「注文住宅じゃなくても、最高の住まいを手に入れたい」——そんな夢を叶える手段として、中古戸建購入×リノベが注目されています。人口減で家が余ることは確実であり、このトレンドは拍車がかかると考えています。
でも、その裏側には多くの“落とし穴”が潜んでいるのも事実。
中古戸建は一軒ごとにコンディションも背景も違い、判断基準を見誤れば「安物買いの銭失い」になりかねません。
この記事では、住宅選びのプロの視点からポジショントーク抜きで、“後悔しない買い方”をお届けします。
目次
| 1. | プロの本音 |
| 2. | 物件選びで見逃せない6つの視点 |
| 3. | まとめ |
1.プロの本音
メリットの裏にある“見えない前提”
中古戸建を買ってリノベする魅力は数多くあります:
- 好立地の物件に手が届きやすい
- 新築より2〜3割安く抑えられる
- 間取りや内装を自由に設計できる
ただし、これらのメリットには見えない“前提”がつきものです。
たとえば「間取りの自由度」は、建物の構造(木造 or ツーバイフォー)によって大きく制限されることがあります。木造なら柱と梁・筋交いで支えているため間取り変更がしやすい一方、ツーバイフォーは壁そのものが構造体となっているため、壊せない壁が多く、思い通りの間取りにできないケースもあります。
また、築古物件では目には見えない配管や断熱材が老朽化していることが多く、これを更新しないまま「表面だけ」リノベしても、10年以内に再工事の必要が生じることも。こうした隠れたコストは見積もりに反映されにくく、最初に想定していた予算を大幅に超えることも珍しくありません。
当然、維持管理の負担はすべて自己責任になります。マンションと違って、戸建には修繕積立金や管理組合がありません。仮に老朽化がそこまで深刻ではなかったとしても、外壁や屋根、水回りなどに不具合があった場合、誰も代わりにメンテナンスしてはくれません。
気づいた時には劣化が進行していて、大規模な補修に数百万円単位のコストがかかる…という事態も珍しくありません。
つまり、“自由で安上がり”というイメージの裏には、『「構造的制約」「見えないコスト」「管理不全リスク」がクリアできたら』という前提条件が隠れているのです。
本当に理想を実現するには、買う前の調査と制約を前提とした設計が不可欠です。安易に夢を描くだけではなく、冷静な現実理解とリスク管理をセットで行う。それが中古戸建リノベのスタートラインです。
2.物件選びで見逃せない6つの視点
視点1|価格の理由に踏み込む
物件価格はその物件の「現実を映す鏡」です。相場より著しく安い場合、必ず理由があります。
| 安さの背景にある主な理由 | 内容例 |
|---|---|
| 老朽化 | 雨漏り、ひび割れ、シロアリ等の劣化が放置されている |
| 法的制約 | 違反建築、再建築不可などで資産価値が伸びない |
| 周辺環境のネガティブ要素 | 騒音、臭気、嫌悪施設の近隣など |
| 過去の事故・事件 | 自殺・事故・孤独死などで心理的瑕疵がある |
たとえば築10年くらいの物件で、屋上やバルコニーの防水が劣化して雨漏りが発生していたり、外壁にひび割れがあるケースも。
これらが放置されており修繕に多額の費用がかかる部位が手つかずのまま残っていることも。こうした物件では、購入後すぐに数百万円単位の修繕が必要となることもあり、“安い”どころか“高くつく”リスクも高いです。
接道義務を満たしておらず再建築不可だったり、建ぺい率や容積率を超えた違反建築で、建て替えや増改築が制限される物件も存在します。これらは銀行の住宅ローンが通らない可能性も高く、売却時に買い手が見つかりづらい=資産価値が下がりやすい物件といえます。例えば築30年で3LDK・駅徒歩10分の好条件なのに極端に安い物件は、こうした“見えない足かせ”を抱えていることが多いのです。
幹線道路や鉄道のすぐ隣にあり、終日騒音や振動が響くような立地。あるいは葬祭ホール、風俗店、パチンコ店、工場など“嫌悪施設”が近接している物件は、日常生活のストレス要因になるだけでなく、将来の転売時に敬遠されるリスクも高いです。例えば「建物の裏手だったのでわからなかったが、よく見たら家族葬ホールが隣に建っていて霊柩車が毎日のように来る」「昼間に見に行ったら静かだったが、夜は騒がしい飲食店街だった」というケースもあり、内見時間帯や周辺の昼夜の雰囲気確認が不可欠です。
事故物件に該当する場合(例:室内での自殺や孤独死)、法律上は一定の告知義務がありますが、どこまで開示されるかは曖昧な部分も。物件の住所でネット検索や近隣ヒアリングも有効な手段です。
このように、価格を判断する際は、「この安さには根拠があるか? そしてそのリスクを自分たちが許容できるか?」を冷静に考える必要があります。
視点2|築年数と耐震基準は“2000年6月”が分かれ目
日本の木造住宅の耐震基準が大きく変わったこの年月以降の物件は、地震に対する構造的な信頼度が高くなります。
また、旧基準の物件では1981年6月より前か後かで、耐震診断・補強工事のコストが大きく変わる可能性があるため、「耐震基準を満たすかどうか」は価格以上に重要な判断基準です。
視点3|徒歩分数では見えない“リアルな生活感”
不動産広告では「駅徒歩〇分」や「買い物に便利」など、利便性をアピールする表現が並びますが、その多くは実生活の感覚とはズレていることが少なくありません。
特に「徒歩◯分」は80メートルを1分とした単純な距離計算が基本。信号待ちや坂道、段差、交通量などは一切考慮されていないため、「徒歩5分」とあっても、実際に歩いてみると体感では10分以上かかることもあります。
たとえば、駅徒歩7分の中古戸建があったとします。
地図上では確かに近く見えるのですが、実際には長い上り坂が続くルート。特に真夏や買い物帰りには体力的負担が大きく、高齢の親との同居を検討していた購入者が断念した事例もあります。
弊社が所在している横浜市も坂が多い土地で、内見の時はわからなかったけど最寄り駅から歩くと急こう配の坂が5分以上続く、みたいな物件も珍しくありません。
特に、ベビーカーを押しての移動をするパパママや、車いすの必要な高齢者の方などは必ず確認が必要になってきます。
あとは、昼間に感じた印象とは全く違う印象を受けることもあります。
駅からの帰路に街灯が少ない、人通りが極端に少ないという場合、昼は全く気にならなったのに、夜には急に不安感を覚えることがあります。慣れるという方もいますが、その感覚は大事にした方が良いです。特に単身女性や子どもがいる家庭では、「明るい夜道」は最も基本的な安心材料です。
また、コンビニが近くても24時間営業でなかったり、病院が近いといっても専門科しかなく、実際の生活では別の医療機関に頼らざるを得なかったといったケースも。
紙面上の「徒歩〇分」や「周辺施設」だけで判断するのではなく、自分や家族のライフスタイルに照らしてリアルに歩いて確認することが、中古戸建購入では非常に重要です。
視点4|境界トラブルと越境問題
中古戸建を購入する際に、見落とされがちだが極めて重要なのが「土地の境界」にまつわるリスクです。
新築住宅では分譲時に測量や境界確定が済んでいることがほとんどですが、中古戸建、特に古い住宅では「どこからどこまでが自分の敷地なのか」が曖昧なケースが多いです。
隣地との境界に関する争いは、感情的な対立に発展しやすく、一度こじれると法的にも精神的にも大きなコストがかかります。たとえば、境界が曖昧なまま所有者が代替わりし、「そこはウチの敷地じゃないのか?」「いつのまにか塀がウチの土地を越えてる」などと主張されるケースも。
また、過去に“近所づきあい”の延長でなんとなく認められていた越境(隣家の樹木や雨樋、塀などが自分の敷地に入り込んでいる)も、売買後に揉めごとの種になることがあります。
越境状態のまま購入すると、将来的な増改築の際に制限が出る場合があります。たとえば、越境部分の撤去を求められた場合、自分の費用で塀を作り直す羽目になることもありますし、逆にこちらが越境していれば、突然撤去を求められて居住環境が変わることも。
また、境界が不明確なままでは、将来売却する際に買い手がつきにくくなり、資産としての流動性も下がります。
購入検討の段階で確認すべき書類は、「確定測量図」または「境界確認書」です。
特に都心部や狭小地では、過去に一度も測量が行われていない土地も少なくありません。その場合、購入前に隣地所有者立ち合いのもとでの測量(民間測量)を依頼し、境界標の有無を確認する必要があります。
このように、境界問題は物理的な不明瞭さだけでなく、人間関係、資産価値、法的リスクをはらんだ複合的なリスク要因です。
中古戸建を選ぶ際には、「建物の状態」や「価格」と同じくらい、「土地の境界」にも真剣に向き合う姿勢が求められます。
視点5|住民像を探る
徒歩1分の範囲内の環境を見ると、その地域の「健全性」が見えてきます。
隣接する住宅が綺麗かどうか。ゴミが落ちていたり、照明が切れたまま放置されていないか。
掲示板の更新頻度。古いチラシが放置されているなら、管理がルーズな可能性が高いです。
ゴミ置き場が乱雑でないか。住民マナーの程度もここで分かります。
これらは、自治会の運営体制や住民の意識を如実に反映しており、購入後の安心感に大きく関わります。
視点6|水回りの移動の限界を探る
戸建てはマンションと違って、床下に配管スペースがあるため、トイレやキッチンの位置変更は原理的には可能です。
ただし、自由度がある=安く済む、ではありません。実際には、排水が“自然に流れる”ための傾斜を取れるか、床下に人が入って工事できるかという2つの物理的ハードルが立ちはだかります。
特にベタ基礎の物件は、床下に人が潜れない可能性があるため、配管を動かすには床をめくって大工事が必要になるケースもあります。せっかく買った物件で「水回りは変えたいけど、予算的に無理だった…」という人も珍しくありません。
さらに見落とされがちなのが、排水マスまでの距離と勾配。トイレや風呂の排水管は、“自然流下”が基本なので、位置を動かすほど傾斜確保が難しくなります。無理に移動させると、排水不良や逆流・臭気のトラブルを招くことにもなりかねません。
リノベ前提で戸建てを買うなら、水回りの位置が最初から適切であるか、もしくは移動にかかるコスト・構造的制約を事前に見積もっておくことが重要です。安く買って自由に間取り変更したつもりが、結局「使い勝手の悪い家」に…とならないよう、慎重に見極めましょう。
4.まとめ
最後に、この記事でお伝えしていることをまとめておきます。
下記のポイントを、ぜひ参考にしてみてください。
- 「立地が良くて安くて自由にリノベできる」は本当にそのまま鵜呑みは危険。構造制約・老朽化・管理不全など、安さの裏には理由がある。
- 成功するには「建物の構造・管理状態・見えないコスト」の理解が必須で、買う前の調査とプロの視点が重要。(ですが、下調べをきちんとしたなら、中古戸建をリノベは非常に良いものになりますよ)
しあわせな家では、中古住宅探しからサポートさせていただき、素敵にリノベーションされたお客様の施工事例を多数ご紹介しておりますので、ぜひご覧ください!